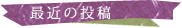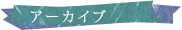宮司だより
宮司だより
- ◆
- 【No.554】※受付終了しました※宮司と学ぶ〜神道〜について
※2月22日の『第48回宮司と学ぶ〜神道〜』は、定員に達したため受付を終了いたしました※
令和8年2月22日(日)9時〜11時『第48回宮司と学ぶ〜神道〜』を開催します。今回のテーマは「遷宮その2」です。
前回に引き続き、伊勢の神宮の「式年遷宮」について取り上げます。
今回は、「式年遷宮」で斎行される一連のお祭りについて、その内容と意義について解説いたします。
お申込みは社務所(03-3429-0869)または本ウェブサイトの右上の「お問い合わせ」にお名前、人数、電話番号、メールアドレスを添えてお願い致します。
令和8年2月22日(日)9時〜11時『第48回宮司と学ぶ〜神道〜』を開催します。今回のテーマは「遷宮その2」です。
前回に引き続き、伊勢の神宮の「式年遷宮」について取り上げます。
今回は、「式年遷宮」で斎行される一連のお祭りについて、その内容と意義について解説いたします。
お申込みは社務所(03-3429-0869)または本ウェブサイトの右上の「お問い合わせ」にお名前、人数、電話番号、メールアドレスを添えてお願い致します。
- ◆
- 【No.553】※受付終了しました※宮司と学ぶ〜神道〜について
※1月25日の『第47回宮司と学ぶ〜神道〜』は、定員に達したため受付を終了いたしました※
令和8年1月25日(日)9時〜11時『第47回宮司と学ぶ〜神道〜』を開催します。今回のテーマは「遷宮」です。
伊勢の神宮では、20年に一度、ご社殿などを新しくする「式年遷宮」が行われます。昨年より、第63回の式年遷宮が始まっており、令和15年には神様に新しいご社殿にお遷りいただく「遷御の儀」が行われます。
遷宮は古くから国内のいくつかの神社で行われておりましたが、現在では修繕がほとんどで完全な造り替えが行われているのは伊勢の神宮だけです。
今回は遷宮の歴史やその内容について、伊勢の神宮以外についても触れながら二回に分けてお話ししたいと思います。
お申込みは社務所(03-3429-0869)または本ウェブサイトの右上の「お問い合わせ」にお名前、人数、電話番号、メールアドレスを添えてお願い致します。
令和8年1月25日(日)9時〜11時『第47回宮司と学ぶ〜神道〜』を開催します。今回のテーマは「遷宮」です。
伊勢の神宮では、20年に一度、ご社殿などを新しくする「式年遷宮」が行われます。昨年より、第63回の式年遷宮が始まっており、令和15年には神様に新しいご社殿にお遷りいただく「遷御の儀」が行われます。
遷宮は古くから国内のいくつかの神社で行われておりましたが、現在では修繕がほとんどで完全な造り替えが行われているのは伊勢の神宮だけです。
今回は遷宮の歴史やその内容について、伊勢の神宮以外についても触れながら二回に分けてお話ししたいと思います。
お申込みは社務所(03-3429-0869)または本ウェブサイトの右上の「お問い合わせ」にお名前、人数、電話番号、メールアドレスを添えてお願い致します。
- ◆
- 【No.552】宮司と学ぶ〜神道〜について
令和7年12月14日(日)9時〜11時『第46回宮司と学ぶ〜神道〜』を開催します。今回のテーマは「海の神様と信仰」です。
前回は「山の信仰」についてお話ししました。今回は海にまつわる神様や、物語について少し深いお話をできればと思います。
海の神様といえば、釣り竿と魚を持った「えびすさま」を思い浮かべる方も多いと思います。海にまつわる神様やお話は神話にもみられます。いざなぎといざなみの間に生まれた「ヒルコ」や、「海幸彦と山幸彦」の兄弟の話が有名です。
今回はさらに浦島太郎のお話や、海洋民族についても触れたいと思います。
お申込みは社務所(03-3429-0869)または本ウェブサイトの右上の「お問い合わせ」にお名前、人数、電話番号、メールアドレスを添えてお願い致します。
前回は「山の信仰」についてお話ししました。今回は海にまつわる神様や、物語について少し深いお話をできればと思います。
海の神様といえば、釣り竿と魚を持った「えびすさま」を思い浮かべる方も多いと思います。海にまつわる神様やお話は神話にもみられます。いざなぎといざなみの間に生まれた「ヒルコ」や、「海幸彦と山幸彦」の兄弟の話が有名です。
今回はさらに浦島太郎のお話や、海洋民族についても触れたいと思います。
お申込みは社務所(03-3429-0869)または本ウェブサイトの右上の「お問い合わせ」にお名前、人数、電話番号、メールアドレスを添えてお願い致します。